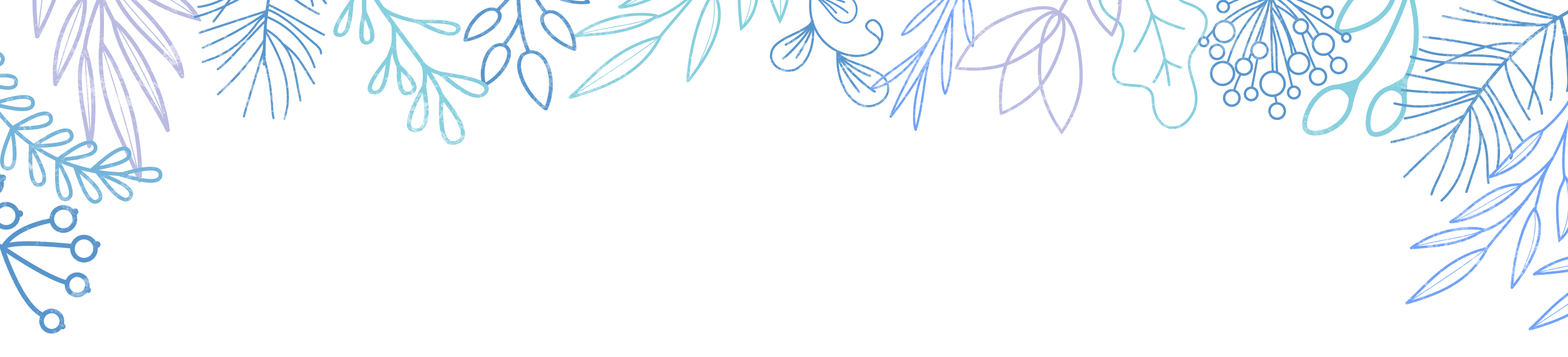この記事はメンタルが疲れやすい人が対象です
「最近、なんだか気持ちが疲れやすい…」
そう感じている方は、もしかしたら自他の感情を混同しやすいのかもしれません。
たとえば、
- 人の言葉に過剰に反応してしまう
- 何も言われていないのに、ネガティブな妄想をしてしまう
- 周囲の雰囲気に敏感で、すぐに疲れてしまう
このような経験はありませんか?
実は、これらの行動は「自分の感情」と「他者の感情」の境界線が曖昧になっているサインかもしれません。
なぜ自他の感情を混同すると疲れるのか?
私たちは、日々たくさんの人と関わりながら生きています。
その中で、相手の気持ちに寄り添うことは大切です。しかし、 「相手の気持ち」と「自分の気持ち」をきちんと区別できていないと、どうなるでしょうか?
例えば、友人が仕事で失敗したとします。
友人は落ち込んでいますが、あなたは「自分が失敗したように感じて」、必要以上に責任を感じてしまうかもしれません。
これは、友人の「悲しみ」という感情を、まるで自分のもののように感じてしまっているからです。
このように、 他者の感情を自分のものとして受け取ってしまうと、自分自身の感情処理能力を超えた負担がかかり、心は疲弊してしまいます。
「相手の気持ちを考えなさい」には落とし穴がある?!
子供の頃、「相手の気持ちを考えなさい」と教わった人は多いでしょう。
もちろん、他者の気持ちに共感することは、円滑な人間関係を築く上で非常に重要です。
しかし、 「相手の気持ちを考えなさい」には、大きな落とし穴がある ことを忘れてはいけません。
それは「自分の心が許容できる範囲のみ」 という大前提があるということです。
どんなに共感能力が高い人でも、すべての人の感情を完全に理解し、受け入れることは不可能です。
自分の心のキャパシティを超えて、他者の感情に飲み込まれてしまうと、メンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があります。
自他の感情を区別するための3つのステップ
では、どのようにすれば自他の感情を区別し、心の安定を保てるのでしょうか?
具体的な方法を3つのステップでご紹介します。
ステップ1:自分の感情に気づく
まずは、 「今、自分はどんな感情を感じているのか?」 を意識的に観察してみましょう。
喜怒哀楽、どんな些細な感情でも構いません。
自分の感情に気づくことで、他者の感情との境界線が見えてきます。
ステップ2:感情に名前をつける
自分の感情に気づいたら、 「これは〇〇という感情だ」 と言葉で表現してみましょう。
例えば、「不安」「イライラ」「悲しい」など、具体的な言葉で表現することで、感情を客観的に捉えやすくなります。
ステップ3:感情の原因を探る
感情に名前をつけたら、 「なぜこの感情を感じているのか?」 その原因を探ってみましょう。
例えば、「プレゼンテーションがうまくいくか不安だ」 「朝の電車が遅延してイライラする」など、具体的な原因を特定することで感情の整理ができます。
これらのステップを踏むことで、 自分の感情と向き合い、コントロールする力 を身につけることができます。
そして、他者の感情に振り回されることなく、健全な人間関係を築くことができるでしょう。
まとめ|心の健康のために、境界線を意識しよう
「メンタルが疲れやすい」「人の言葉に過剰に反応してしまう」と感じている方は、 「自他の感情の混同」 をしていないか、振り返ってみましょう。
「相手の気持ちを考えなさい」という言葉は、 「自分の心が許容できる範囲のみ」 という大前提を忘れないようにすることが大切です。
自分の感情に意識を向け、他者との適切な境界線を引くことで、心の安定を守り、より穏やかな日々を送ることができるはずです。